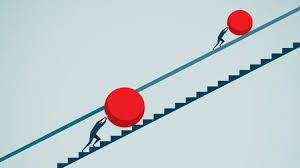難しいインプットを正確にする私の方法
本日は「難しいインプットを正確にする施策」というテーマでお話